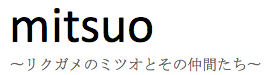あまりブログを更新できませんでしたが、2023年を振り返っておきます。
最も大きな出来事は、3月から5月にかけてモエギハコガメを3頭も死なせてしまったことです。
いずれも十年来の飼育個体であり、存在していることが当たり前になっていたので、非常に悲しい思いをしました。
最終的な診断は腎不全でしたが、どうして罹患したのかは分かりません。
獣医師さんによると冬場のクーリングが原因ではないかとのことですが、この数年はあまり冷やさずに越冬させていたので、私は違うと思っています。
何年も同じサイクルで飼育してきた個体が同時期にバタバタと死んでしまうのは偶然ではなさそうですが、一つだけ思い当たる原因は屋外飼育による夏場の暑さです。
今年は特に異常な暑さでしたが、昨年までの猛暑も生体には負荷が大きかったでしょうから、体力のない個体から弱ってしまったのかなと。
本来棲息すべき気候とは異なる環境で長年飼育されてきたわけですから、少しずつ悪化していたということなのかもしれません。
ずっと調子良く飼えていると思い込んでいた自分が恥ずかしいです。
そして、もう一つの大きな出来事は、庭で飼育している亀たちがドブネズミに襲われてしまったことです。
特にカンボジアモエギは両腕を激しく食いちぎられ、かなりの重傷でした。
出血も酷くて死んでしまうかもしれないという状況でしたが、ひと月以上の拒食の後に少しずつ食べ始め、なんとか回復に至りました。
既に3頭も死なせた後でしたので、命が助かっただけでも本当に良かったのですが、この事で全ての亀を屋外飼育から撤退することに。
その後に金網の蓋を付けたブルコンを用意してアメハコとドロガメのみを庭へ戻しました。
今さらですが、2021年の10月にガルフ同士がケンカをしたと思っていた怪我もドブネズミの仕業に間違いないでしょう。
亀たちに謝らないといけません。
いずれにしても、屋外飼育が大幅に制限されてしまったことで、私の亀飼育は方向転換を強いられることになりました。
これまで庭で飼育してきた個体達が室内のケージで過ごす様子を見るのは非常に辛く、なんとかしてあげたいのですが、もともとギリギリのスペースまで使用していましたので、飼育数を減らさない限り改善は難しそうです。。。
と言いつつ、、、
今年も色々と欲しい生体に悩まされました。
特に我慢したのはシロアゴヤマガメとモリセオレガメです。
この両種は私の好みにピッタリですので、いつかは飼ってみたいと常に思ってきました。
ただ、現在飼っている種や個体を理解できていない現状で難しそうな種を増やすことに抵抗もあり、なんとか思い留まりました。
今は、新たに迎えたセマルハコガメのベビー達を育てることを楽しんでいます。
それと、夏にユカタンハコガメの2022CBを迎えました。
ブリーダーさんの話ではオスの可能性がありそうなので、期待しつつ育てようと思います。
繁殖については、親個体すら満足に飼育できていない状態ですので、あまり積極的に考えることができません。
ただ、事情があってセイロンホシガメを雌雄同居させたことは大きな変化かなと思っています。
また、今年はトウブドロガメが孵ったのですが、ただ飼っているだけで殖えたという印象が強く、生命力の強さに驚きました。

日頃から手の掛かる種ばかりを好んで飼育している自分は、成体を販売する際に用いられる「即戦力」という表現に嫌悪感を抱いてきたのですが、少し理解できたような気がしました。
こうして今年一年を振り返ってみると、辛かったことの方が目立ちますが、あくまでも趣味としての亀飼育ですので、充分に楽しませてもらえたと思っています。
来年は、どんな年になるのでしょうか。。。
爬虫類イベントを取り巻く環境や異常気象等、心配事は尽きませんが、前向きに続けていきたいと思います!
それでは、良いお年をお迎えください!!